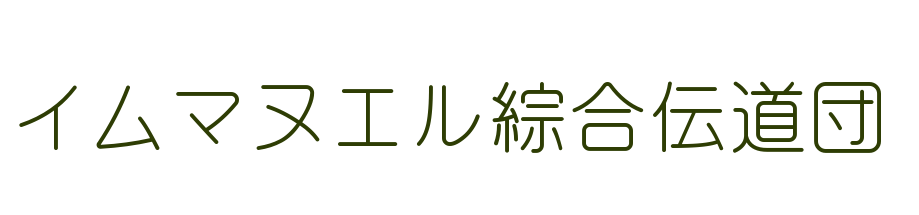フィリピンでは8月から台風、熱帯低気圧、地震などによる災害があちこちで起こっています。そのような中、洪水対策のための予算が支出されても事業が行われない「幽霊事業」が国会で明らかにされ、国民の間で批判が起こり、マニラでは汚職に抗議する大規模なデモが行われました。
【フェイスアカデミー理事会の活動】
夏休みが明けて新学年度が始まり、恭子にとって理事としての2年目の働きがスタートしました。今年は新たに5名の理事が加わり、男性陣は4カ国から7名という国際色豊かな顔ぶれとなりました。一方、女性陣8名は、恭子を除いて同じ国の方々で構成されています。
新年度の初めには、恭子を含む3名の理事で特別小委員会が設置されました。その中で、最も時間の融通が利く恭子が委員長を務めることとなりました。役割は会議の日程調整や会場確保といった運営面での調整に限られ、議事録や公式文書は英語を母語とする委員が担当しています。学校の管理職との会議も良い学びとなっており、小委員会は年内の活動完了を目標に進められています。
この活動の中で、恭子はふと夏目漱石『草枕』の冒頭を思い起こしました。「山路を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。」

特定の課題に取り組むために設けられた特別小委員会だからだと思いますが、恭子は同時に次の聖句を心に留めるようになったといいます。「最初に訴える人は正しいように見える。その相手が来て、彼を吟味するまでは。」(箴言18:17) 何よりもまず「神の国と神の義」を求める姿勢をもって臨み、上からの知恵を祈り求めながら、また愛をもって取り組むことを委員会で確認しつつ、活動を進めています。
そのような中、コロナ以降初めて(少なくとも5年ぶり)となる理事の1泊2日の勉強会が行われました。勉強会では Steve Cuff 氏の著書 Managing Leadership Anxiety (Yours And Theirs) を読み、感想や学びを分かち合いました。翌日は宿泊先で通常の理事会が開かれ、会議の終了と共に解散となりました。
小委員会の委員長を務めるようになって以来、特に男性理事から「対等な仕事仲間」として受け入れられている実感を持っていた恭子ですが、今回の合宿ではほぼ全員で宿泊と三度の食事を共にしたことで、単なるチームの結束以上に「目的に対する全員でのコミットメント」を確認できる良い機会となりました。
【祈祷課題】
- 学期間休みに入った学生たちが、誘惑や過ちから守られ、霊肉共に支えられ、第2学期(11月中旬)に帰ってこられるように。
- 子どもたちが学校生活(学びと言語)に順応し、救いへと導かれるように。
- 家族が事故・事件・怪我・過ち・災害・病気・疫病などから守られますように。